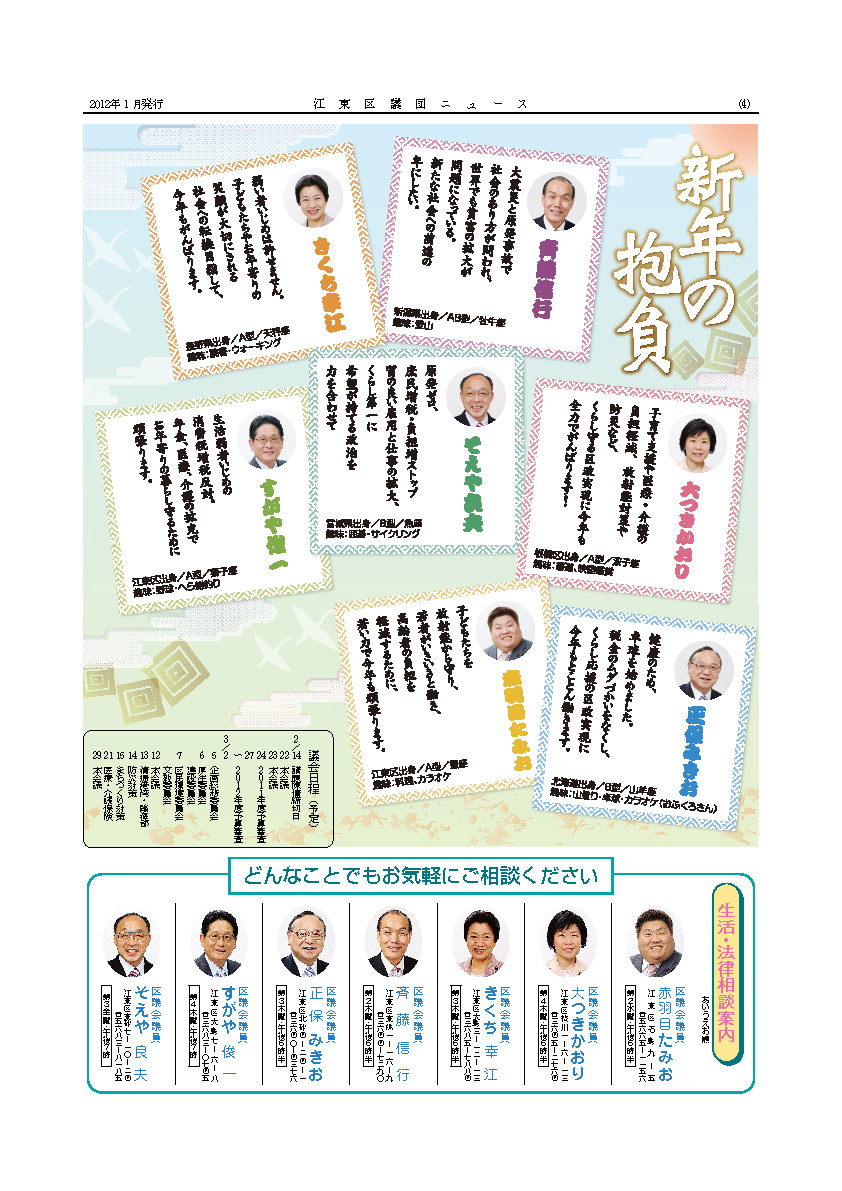各紙面をクリックするとPDFファイルで閲覧できます 続きを読む
区議団ニュース2012年7月号「くらしも経済も破壊する消費税増税は許されない!」
各紙面をクリックするとPDFファイルで閲覧できます 続きを読む
江東区民アンケート実施中!
皆さんの声をお聞かせください。
江東区民アンケート実施中!
記入はこちらから。
http://www.jcp-kotokugidan.gr.jp/cgi-bin/enq12/questionnaire.html
平成24年度江東区一般会計予算に対する修正の提案説明
平成24年度江東区一般会計予算に対する修正案についてご説明いたします。
昨年3月11日に発生した東日本大震災は、多くの尊い命を奪い、国民の暮らしにかつてない危機的な状況をもたらしました。震災からの復興は緒についたばかりで、ましてや福島第一原発の事故は、いまだ暮らしや経済に深刻な影響を及ぼしています。こうした中、政府が「社会保障と税の一体改革」で、消費税増税と社会保障の切り下げを実施すれば、暮らしや経済にさらに打撃を与えることは明らかです。
いま江東区政には、区民の不安を取り除き、暮らしを守る役割を果たすことが求められています。その立場から、本修正案を提案するものです。
修正案の柱は、第一に、区民の強い要望である福祉や教育、中小企業支援の充実、防災対策や放射能汚染対策の一層の強化などを行うこと。第二に、文化センターやスポーツ施設等の使用料値上げなど新たな負担増を中止するとともに、行革の名による民間委託を中止し、正規職員を採用することにより区民福祉の向上を図ること。第三には、区民の立場で不要不急の事業を削減するとともに基金の活用を図り、住民要望に積極的に応える財源を確保するものです。
以下、内容についてご説明いたします。
平成24年度一般会計予算において、歳出、歳入予算1614億9100万円を20億8029万3千円、予算原案に対し1.2%増額し、総額1635億7129万3千円といたしました。
歳入のうち、第13款、使用料及び手数料は、区民館等の施設使用料値上げの中止で117万円余減額いたしました。第16款、財産収入は、株式会社東京臨海ホールディングス社への出資金を全額回収し、2億4千万円を収入として見込んだものです。第17款、寄付金では、マンション建設にともなう公共施設整備協力金について、収入が見込まれる額の一部である4億円を計上いたしました。第18款、繰入金では、基金から14億4千万円余の繰入れを行い、必要な財源を確保いたしました。
次に、歳出の修正について主なものを申し上げます。
第1款、議会費は、議長交際費を30%削減いたしました。
第2款、総務費では、区長交際費の削減、同和対策費の全廃、副区長を一人にするなど経費の節減を行う一方、平和都市宣言趣旨普及事業、公契約条例制定のための調査費、津波・高潮対策促進のための調査・研究費を増額いたしました。
第3款、民生費では、中国残留邦人生活支援センターの土・日・夜間等の開設を行うほか、難病患者への福祉タクシー券支給、民設民営の障害者・児通所施設への水、毛布等の災害時備蓄物資の支援、障害児の施設利用料補助を実施いたします。また、高齢者対策では、介護従事者確保のための家賃補助を継続、介護保険の保険料及び利用料の負担軽減対策の実施、重度介護手当や高齢者への入院助成金の支給とともに、特別養護老人ホーム整備のための調査費を計上いたしました。
さらに、子育て支援では、公立保育園の給食の新たな民間委託の見直し、保育園の待機児解消を図るため、認可保育園の増設、ひとり親家庭のホムヘルパー派遣の新規受付の継続を図ります。生活保護事業では、不足するケースワーカーを16名増員することなど、あわせて10億800万円余を増額いたしました。
第4款、衛生費では、食品の放射能測定の体制強化、区民貸出し用の空間放射線量測定器を購入するほか、前立腺がん検診の対象年齢の拡充、高齢者のインフルエンザワクチン接種の無料化を65歳以上からとするなど、1億円余を増額いたしました。
第5款、産業経済費では、青年就労相談窓口の設置、小規模特別融資の利子補給の補助率引き上げ、商店街装飾灯電気代の全額補助等で8400万円余を増額いたします。
第6款、土木費では、中小企業の仕事確保のための民間住宅のリフォーム助成事業の実施、耐震シェルター購入助成やマンションの耐震改修の補助額引き上げ等で7億4800万円余の増額を行う一方、地下鉄8号線建設基金の積み増しの取りやめで5億円を減額いたしました。第7款、教育費では、小一支援員の通年配置、就学援助の拡充、学校司書配置の拡充、幼稚園の保育室へのクーラー設置、学校用務や警備員、図書館窓口業務の民間委託の中止など、5億8400万円余を増額いたしました。
以上、ご理解のうえ、ご可決くださいますようお願いいたしまして、提案説明といたします。
2011年第4回定例会-きくち幸江議員(行財政改革・高齢者・教育)
2011年11月25日(金)2011年第4回定例会-きくち幸江議員
- 江東区行財政改革計画について
- 高齢者の生活支援について
- 教育問題について
[議会発言映像=クリック](区議会サイトへ)
日本共産党江東区議団を代表して質問します。
質問の第1は、江東区行財政改革計画についてです。
まず、区民負担と徴収強化について伺います。
計画では、保育料や使用料の引き上げのほか、新たにがん検診の有料化が打ち出されました。また、区税や国民健康保険料などの徴収強化で、強制徴収、タイヤロックなども行うとしています。しかし、なぜ今値上げなのでしょうか。区民の暮らしは大変です。飲食・小売業は売り上げが減り、商店街の衰退に歯どめがかからず、建設業など自営業も仕事がない、生活できないと悲鳴が上がっています。医療費や教育費負担などが重く、生活保護世帯の急増が社会問題となるほどに困窮度を増している区民生活の現状を、どう受けとめていますか。
保育料などの利用料は、受益者負担の適正化で値上げを検討するとしていますが、区が行っている事業は、生存権の保障、区民福祉の向上という、国と自治体の目的のもとに税金を使って当然に行うべき仕事です。
江東区の財政は、昨年度も42億円の黒字で基金も潤沢です。負担の適正化と言うのであれば、区民生活の現状に照らして負担を軽くし、区民生活を応援すべきではありませんか。見解を伺います。
徴収強化も問題です。これまでも指摘してきましたが、国民健康保険料などの滞納世帯の多くは払いたくても払えない低所得世帯です。徴収強化方針のもとでは、銀行口座を凍結された高齢者が餓死して発見される、営業用の自動車を差し押さえられ仕事ができなくなった業者が自殺するなど、全国で悲惨な状況が広がっています。命を守る社会保障の制度により命が奪われるような徴収強化は許されません。見解を伺います。
がん検診は、がんの早期発見・早期治療により本人の命を守ると同時に、重症化を防いで医療費が軽減されることから、受診率を上げる努力がされてきました。受診抑制につながる自己負担の導入はこうした努力に逆行します。検診は基本的に無料を維持し、自己負担が4,000円かかるヒブワクチンなどの予防接種を含め負担の軽減を図るべきです。伺います。
次に、民間委託についてです。
新たに保育園4園の民間委託を初め、児童館、福祉会館、図書館など、地域にあるほぼ全施設が委託の検討対象とされています。区民サービス向上のためといいますが、保育園の委託ではこれまで父母の強い反対がありました。現在の入所者の卒園を待って委託をするのは、父母の反対を恐れたこそくなやり方ではありませんか。
また、委託園を勝手に決め、父母や関係者の意見も聞かずに委託を前提とした募集を始めていることは、住民軽視、議会軽視であり、区のスローガン「みんなでつくる江東区」にも反します。こどもたちの成長に大変な負担となり、効率優先で保育の質の低下をもたらす保育園の委託は撤回すべきです。伺います。
次に、職員削減についてです。
災害時に対応する職員が足りないではないかと指摘をしてきましたが、区は、協力業者の動員で間に合うとしています。しかし、みずからも被災しながら昼夜を分かたず区民のために働き、被害状況を判断して機敏に対策をとる責任と権限を持っているのは正規職員です。出先施設や公園、道路を整備する仕事で日常的に地域とつながり、地域をよく知っている正規職員がいてこそ、避難所運営を初め復興に向けての仕事を区民と一緒に進めることができると思いますが、見解を伺います。
次に、自治体の役割についてです。
そもそも全国の自治体で進められている行政改革は、政府の強い指導のもとに行われています。厚生労働省は、保険料徴収率にペナルティーをつけ、強制徴収のやり方などの研修を行う。総務省は、技能職の退職不補充や民間委託を求める通達を繰り返し出すなど、さまざまな手法を駆使してその進捗状況で自治体を評価する一方、ことし成立した地域主権一括法では、福祉や医療・介護、教育を初め、道路や河川、まちづくりに至るまで、国の責任を投げ出そうとしています。その上、税と社会保障の一体改革では、年金を含むすべての社会保障制度の給付の縮小と負担強化を、住民と自治体に押しつけようというのです。
区の行政改革の目的は、「区民サービスの維持」と「区政運営の安定」といいますが、国の言いなりに区民負担をふやし、行政の守備範囲を狭めることは、区民生活と自治体の破壊につながる道ではありませんか、伺います。
江東区政に今求められていることは、基金も活用して不足する施設の建設や区民負担の軽減、地域経済の活性化などに思い切って取り組むと同時に、大企業への行き過ぎた減税などを進める国の逆立ち政治を正し、憲法と地方自治法の原点に立ち戻って、国民生活を守る責任と負担を国と都に強く求めるべきと思いますが、見解を伺います。
次に、高齢者の生活支援について伺います。
第1に、介護保険についてです。
来年4月からの制度改定に向けての政府方針はいまだ確定せず、「保険あって介護なし」と言われる制度設計の矛盾が噴出しています。保険料の負担はもう限界なのに値上げを前提とした検討が進められています。
本区は、基金の活用で多段階化を含め検討するということですが、住民税課税の最低クラスのところで税や医療費の負担感が大きく、滞納世帯の比率も高くなっています。このランクの引き下げを含め、値上げにならない設定を求めます。伺います。
利用料負担も大変で、ケアプランづくりの際には「月5,000円まで」など、使える金額で制限されてしまう状況があると聞いていますが、今検討されている中には、一定水準の所得で利用料を2倍にすることや、施設入所者の居住費の値上げ、ケアプランの有料化などが提案されています。これ以上の負担増とならないよう、緊急に政府に申し入れるべきと思いますが、伺います。
また、こうした負担増は、今年度で終了する介護従事者の労働条件改善のための交付金にかわる財源としての提案ということです。介護報酬に組み込まれては保険料や利用料にもはね返ります。これまでどおり別枠で国庫負担とし、さらに労働条件の改善を図って必要な人材確保ができるよう政府に求めるべきです。あわせて伺います。
今回の制度改定で一番の問題は、地域包括ケアを強調しながら、軽度の要介護者を保険給付から外す仕組みがつくられたことです。この介護予防・日常生活支援総合事業について、区は慎重に対応するとしていますが、人材確保や財源の制限があり、必要なサービス供給ができる保証はありません。総合事業の導入はやめ、従来の介護予防サービスとあわせて、区の福祉施策であるひとり暮らし高齢者の支援やおむつ支給なども拡充し、自立した生活を維持できる体制整備を進めるべきと考えますが、伺います。
次に、特別養護老人ホームの緊急整備についてです。
2,000人近い待機者に対し、区の今後の計画は1施設のみと後ろ向きです。この間、医療経済研究機構の調査結果をもとに、本当に必要な人は待機者の1割という議論がありましたが、同じ調査では、4割の人が1年以内に入所が必要であるとされています。また、区の調査で、高齢者の6割が在宅を望んでいるといいますが、介護に対する区への要望の1番に、特別養護老人ホームなどの施設整備が上がっています。在宅ケアも不十分な中で、家族の負担も限界という世帯がふえています。現状を受けとめて待機者解消に見合う整備計画をつくるべきと思いますが、伺います。
次に、高齢者の住宅問題についてです。
在宅介護、在宅医療を強調されても、高齢になって住み続けられる住宅が圧倒的に不足し、とりわけ賃貸住宅に居住する高齢者への支援が急務となっています。法改正により、サービスつき高齢者住宅がスタートしましたが、低所得者は入れません。高齢者への住宅あっせんの成立が年間数件と低い状況に対し、区は、居住支援協議会であっせん方法を工夫するとしていますが、最大の問題は家賃です。公営住宅が圧倒的に足りない状況に対し、収入に応じた家賃で入れるよう家賃助成の制度をつくるべきです。伺います。
UR賃貸住宅では高齢化が深刻で、大島六丁目団地自治会がことし行った調査では、世帯主が60歳以上となる世帯が7割に上ったとのことです。年金生活に入って収入が減り、年収200万円未満の世帯が3割、375万円未満でも7割を占めるのに対し、家賃は安くて7万円、10万円以上の世帯も2割を超えています。
本区には、1万7,000戸のUR賃貸住宅がありますが、1970年代に建設された住宅はどこも高齢化が深刻です。政府に対し、UR賃貸住宅は公共住宅としての位置づけを持たせ、収入に応じた家賃で住み続けられる制度に改めるよう求めるべきです。伺います。
次に、教育問題について伺います。
第1は、教科書採択についてです。
ことし8月に、来年度から中学校で使う教科書の採択が行われました。本区議会を初め、全国各地の議会で質問や決議が行われるなど、これからの教育にかかわる問題となっています。
採択をめぐって市民の反対集会などが開かれ、特異な教科書として問題となっているのは育鵬社、自由社の発行する歴史・公民の教科書です。この教科書をつくった人たちは、日本が起こした戦争を侵略戦争として反省することを自虐史観と攻撃し、教科書では、自存自衛のため、アジア解放の戦争であり、戦争は正しかったとこどもたちに教えようとしています。しかし、日本が起こした戦争が侵略戦争であったことは国際的に認められた認識です。
1995年、当時の村山首相が、植民地支配と侵略によってアジア諸国の人々に多大の損害と苦痛を与えたと、反省とおわびを表明しました。この発言が世界に向けて発せられた日本の公式見解であると思いますが、区教育委員会の見解を伺います。
憲法に対する認識も問題です。育鵬社の公民の教科書では、天皇を絶対的な権力者とした戦前の大日本帝国憲法を持ち上げる一方で、現憲法はGHQに受け入れさせられたとして改憲が強調されています。しかし、現憲法は、悲惨な戦争は二度としないという決意と反省のもとに、国民自身がいろいろな試案を作成し、国民的議論を経て日本の国会で決められました。当時の文部省が新しい憲法をこどもたちに教えるためにつくった教材の中でも、日本国民全体の意見で自由につくられたものでありますと教えています。
21世紀の今日、国際紛争の解決は、武力に頼らず話し合いで解決しようという流れは世界に広がり、日本の憲法9条の評価も高まっています。日本に育つこどもたちが国際社会の一員として、アジアの人々とともに平和的友好関係を築いていく上でも、恒久平和、基本的人権の尊重、国民主権、男女平等といった現憲法の理念をしっかり踏まえた教科書であるべきと考えますが、見解を伺います。
次に、教員の役割についてです。
日本の政府も採択に加わったILO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告」では、「教員は教科書の選択並びに教育方法の適用に当たって不可欠の役割を与えられるものとする」とされています。全15冊もの教科書を選ぶには、現場で教科書を使う教員の専門性は最大限尊重されるべきです。見解を伺います。
次に、少人数学級についてです。
どの子も一人一人十分な教育を受けて成長、発達できるように環境整備を進めることが、何より教育行政に求められています。少人数学級の取り組みは全国の自治体で進められ、学力の向上や生活面での落ち着き、不登校児童の減少など、その効果が認められています。
今年度、ようやく国において小学校1年生で35人学級となりましたが、予定されていた小学校2年生での実施は、予算上来年度に先送りとなりました。順次全学年に広げていく計画が着実に進められるよう、強く政府に求めるべきと思いますが、伺います。
次に、教育費負担の軽減についてです。
義務教育費無償の原則にもかかわらず、無償の対象は授業料や教科書代に限られ、制服や体操着、ドリル代、修学旅行の積み立てなどの支出で、家計負担が大変です。経済的負担の増加は、内閣府の調査でも子育て世代の不安のトップで、児童虐待の要因としても重要視されています。授業に必要なドリルや遠足、学校行事費用は公費負担とすべきです。また、就学援助の補助対象を、少なくとも23区平均の生活保護基準の1.2倍に広げることを求めます。見解を伺い、質問を終わります。(拍手)
2011年第4回定例会-菅谷俊一議員(防災・放射能汚染・TPP)
2011年11月24日(水)2011年第4回定例会-菅谷俊一議員
- 防災対策について
- 福島原発事故に伴う放射能汚染問題について
- TPP・環太平洋連携協定問題について
[議会発言映像=クリック](区議会サイトへ)
日本共産党区議団を代表して、大綱3点について質問いたします。
質問の1点目は、防災対策について伺います。
3月11日の東日本大震災を受け、国及び都の防災会議は、東京都の被害想定の見直しに向けた検討を始め、これまでの地震想定マグニチュード7.3から関東地震のマグニチュード8級を想定する方向が検討されています。
一方、国や都の被害想定の見直し待ちではなく、港区を初め都内の自治体でも、地域防災計画の見直し、総点検の動きが強まっています。
世田谷区は、原子力発電所の事故や津波対策を含む70項目の災害対策の総点検を行い、地域防災計画を見直します。また、町田市も、原子力災害への対応を盛り込むなど、地域防災計画の見直しの検討が行われています。
これまで区は、被害想定や地域防災計画の見直しは、国や都の改定待ちとしてきました。本区は、大半が海抜ゼロメートル地帯に加えて、分厚い軟弱地盤上に立地するなど、地震や水害に極めて弱い地域です。関東大震災の経験や東日本大震災を踏まえ、区が独自に災害想定を引き上げ、原子力災害への対応を含む地域防災計画の総点検、見直しが急務だと思いますが、区長の見解を伺います。
首都での大地震発生の確率が高まるもとで、第1に急ぐべき課題は、木造家屋などの耐震化の促進です。特別区協議会で震災対策の講演会が開催され、阪神・淡路大震災では、発生15分で3,300人が家屋倒壊で命を落としたとして、住宅の耐震補強と家具の転倒防止の必要性が改めて強調されました。区が8月に行った防災に対する区政モニターアンケートでも、区に望む防災対策のトップは、家屋の耐震補強の充実です。
ところが、区の住宅耐震化の取り組みの現状は、目標の2万7,000戸に対し、住宅耐震改修の助成制度開始以来5年間で、木造住宅では17件、病院などの民間特定建築物の実績はありません。木造家屋の耐震化の平均費用は約300万円と聞いております。耐震改修の助成額の再引き上げなど、耐震化促進を強化するべきです。伺います。
また、区は、部分耐震などの簡易耐震改修への補助を行っていません。未耐震の住宅には、高齢者世帯も多く、経済的困難等を抱えています。地震発生時の家屋倒壊から何よりも住民の命を守ることを最優先に据えて、23区で広がっている部分耐震や耐震シェルター設置にも助成を行うべきです。伺います。
第2には、65歳以上の高齢者世帯などに対する家具転倒防止器具取付事業の改善、普及です。
現在、ひとり暮らしを含む高齢者世帯、約4万3,000世帯に対し、取りつけ実績は約1,700世帯です。東日本大震災以降、申請がふえ、取りつけまでに3カ月も待たされると聞いています。現在の1社のみの業者対応を改め、本区と提携がある住宅リフォーム協議会などを活用するなど、器具取りつけを早め、普及促進を図るべきです。また、器具取りつけ数を、区民の希望に応じてふやし、ガラス飛散防止フィルムの張りつけなども助成対象にすることを求めます。伺います。
第3には、帰宅困難者対策と高層住宅対策について伺います。
港区は、東日本大震災時に多数の帰宅困難者を抱え、高層住宅のエレベーターが長時間停止したことなどの事態を踏まえ、10月に防災対策基本条例を制定しました。条例には、区内事業者に対する責務として、周辺地域住民の安全確保や区の防災対策事業への協力とともに、一斉帰宅の抑制と帰宅困難者への食料備蓄を定めています。
また、高層住宅の対策では、防災計画策定や救出、避難に必要な用具の備蓄と、建築主には備蓄スペースの確保を定め、区長はそのために必要な支援を行うとしています。
本区には、12階建て以上の高層住宅で680棟以上、17階建て以上の超高層住宅では117棟もありますが、マンション等の建設に関する条例で災害用格納庫の設置を定めたほかは、防災の啓発活動が中心です。区内の高層住宅や大規模、中規模の主要な事業所、大学などに対し、防災計画策定や防災機材の備蓄、帰宅困難者対策としての食料備蓄などについて、実態調査を早急に行うべきです。
また、本区も、条例化に向けた検討が必要と考えますが、区長の見解を伺います。
第4には、津波、高潮などの水害対策について伺います。
津波対策を求める我が党の本会議質問に対して、これまで区は、「都の被害想定の見直しを待ってから」との消極的な姿勢でした。品川区の濱野区長は、「東京湾が震源の場合も想定し、対応可能な部分を先に進める」として、護岸調査や避難方法、過去の津波、高潮の被害などの基礎調査を行い、津波・高潮ハザードマップ作成を目指すとしています。
港区では、学識経験者による津波・液状化対策に関する検討部会を設置し、被害予測と対策の方向を今年度中に示すとしています。東京都待ちの姿勢を改め、津波対策の検討を始めるべきです。伺います。
防潮堤の強化も急務です。大きな津波ではなくても、直前の直下型大地震で防潮堤や水門が破壊され、水害発生の危険もあることを専門家から指摘されています。現在、東雲や有明地区等の一部では、防潮堤の耐震補強が未完了と伺っています。関東地震級の揺れや地盤の液状化による側方流動などにも対応する耐震補強とともに、津波対策に向けた護岸のかさ上げなど、都に緊急要請すべきと考えますが、区長の見解を伺います。
津波や洪水などの水害時に区民が避難できるよう、区と区内大手企業4社とで災害時協定を結んだことは一歩前進です。大阪市では、32万人分の津波避難ビルの確保に向け、公共施設185カ所の指定を初め、ホテルプラザオーサカの指定など、1万棟を対象に働きかけるとしています。
本区でも、津波避難ビルの指定促進に向け職員を増員するなど、事務所ビルや高層住宅の所有者、居住者への働きかけを急ぐことを求めます。伺います。
区は、津波の想定が決まれば、洪水ハザードマップとは別に津波ハザードマップが必要だとしています。指定された津波避難ビルを表示するなど、地域別の津波ハザードマップ作成を急ぎ、区民に全戸配布することを求めます。伺います。
また、区は、津波や洪水による浸水は長期間となり、水害用機材の備蓄は困難としていますが、これでは住民の命と暮らしは守れません。公共施設に水害用機材の配置を、消防署など関係機関と協議、連携して検討すべきと思いますが、伺います。
質問の2点目は、福島原発事故に伴う放射能汚染問題について伺います。
福島第一原発事故の発生から8カ月がたちましたが、いまだに毎時数億ベクレルの放射性物質が環境に放出され、収束の見通しがついていません。千葉県柏市では、市の所有地から極めて高い放射能が測定されたほか、足立区を初め、都内各地でも許容放射線量の年間1ミリシーベルトを超える場所が、住民グループなどによる自主的な測定で相次いで見つかり、自治体によるきめ細かな測定と速やかな除染が求められています。
こうした中で、「放射能からこどもを守ってほしい」との区民要望の高まりを受けて、区は、学校や保育園、公園などの空間放射線量の測定については、516施設から537施設にふやし、測定ポイントも、現行4地点から側溝や雨水ますなどを加え、10地点にするとしています。
こどもが集まる場所の測定ポイントは、10地点と限定するのではなく、放射能がたまりやすい場所をきめ細かく測定することが、保護者、住民の安心につながると思いますが、伺います。
また、専門家は、公共施設以外の民有地なども含め、放射性物質が集中しやすい場所を測定し、早く除染することが重要だと指摘しています。
柏市を初め、新宿区や中央区、港区では、住民の希望に応じて測定器を貸し出し、放射線量が高い場所は再測定して除染するとしています。区として、測定器を十分確保し、区民への貸し出しを行うなど、住民参加のもと地域ぐるみで取り組めるための支援も必要と思いますが、伺います。
現在、都は、江東区内にある都立公園や都立高校、特別支援学校などでの放射能の測定調査を行っていません。都に対して直ちに実施するよう求めるべきです。あわせて伺います。
「年間1ミリシーベルト以上の箇所は、除染の支援を行う」との国の基本方針が示され、区は、国の基準や指針などに準拠して除染を行うとしています。こどもが集まる保育園や幼稚園、小学校などは、地表50センチメートルで1時間当たり0.23マイクロシーベルトを超える箇所、また、中学校では、地表1メートルで0.23マイクロシーベルトを超えた箇所としています。
川崎市では、市長が、「国の決める数値よりも厳しく、きめ細かに対応し、市民の不安を解消する」として、地表5センチメートルで毎時0.19マイクロシーベルト以上の値で除染を進めています。
放射能による健康被害には、これ以下の放射線量なら安全という「しきい値はない」という国際的な共通認識に基づき、せめて川崎市の基準で除染することを求めます。伺います。
放射能汚染の広がりに対し、安全な食品を求める区民や国民世論が高まり、国は食品の暫定規制値を来年4月から見直すとし、セシウムでは、暫定規制値の5分の1にするとしています。水や牛乳などの飲み物では、現行1キログラム当たり200ベクレルが40ベクレルに、また、米や野菜などの食べ物では500ベクレルが100ベクレルになると予想されます。しかし、国際的な基準から見れば、この見直した値でもまだ高く、飲み物では、WHO(世界保健機関)が、セシウムで10ベクレル、食べ物では、ロシア、ベラルーシのこどもへの規制値は、セシウムで37ベクレル、ドイツ放射線防護協会では、成人でも8ベクレルです。
区は、国に対して、国際的基準を踏まえた規制値の再検討とともに、こどもの規制値はより厳しい設定にするよう求めるべきです。伺います。
同時に、最新の検査機器を最大限確保し、万全の検査体制の構築を国に要請すること。また、自治体の検査機器購入に対する補助制度の拡充も要請するべきです。あわせて伺います。
区においては、牛乳などの放射能検査を実施したほか、学校給食の食材検査に向け、検査機器の購入を決めたことは評価するものです。今後、区民が希望する食材検査にも対応するよう、体制整備の拡充を求めます。伺います。
次に、江東区地先の中央防波堤埋立処分場への放射性廃棄物の受け入れについて伺います。
都は、高放射能で汚染された23区内の下水汚泥焼却灰や清掃工場のごみ焼却灰を、中央防波堤埋立処分場に持ち込み、埋め立てや一時保管を行ってきました。下水汚泥焼却灰だけでも1日100トン排出され、既に2万5,000トン受け入れたと伺っています。10月時点でも、1キログラム当たりで、葛西水再生センターの下水汚泥焼却灰が1万9,000ベクレル、江戸川清掃工場の焼却灰で1万3,000ベクレルの高い放射能が計測され、都民や区民から不安の声が上がっています。
こうしたもとで都は、最高で1万7,000ベクレルを計測した多摩地域の下水汚泥焼却灰の持ち込みまで開始しています。現在、下水汚泥焼却灰の埋め立て場所からは、年間許容量の1ミリシーベルトを超す放射線量が測定されています。都は、一連の高放射能焼却灰の最終処分場持ち込みに際して、区民への説明会を行っていません。放射能汚染に対する区民の不安が大きく広がっています。区南部地域などで住民説明会を実施し、住民の理解と合意のもとで行うべきではありませんか。また、区としても、こうとう区報などで区民に随時現況を知らせるべきです。区の見解を伺うとともに、都に対して、住民説明会の実施と多摩地域内での処理体制の早期確立を求めるべきです。伺います。
質問の3点目は、TPP・環太平洋連携協定問題について伺います。
11月11日、野田首相はTPP交渉参加に向け、関係国との協議に入ることを表明しました。日本共産党は、全国で急速に広がる反対世論を無視し、国民への説明もないままTPP参加に踏み出したことに強く抗議し、その撤回を強く求めるものです。
TPPは関税を原則撤廃して農産物の輸入を完全に自由化し、さらに、非関税障壁という貿易制限も撤廃されます。TPP推進の中心はアメリカであり、国内では大企業、財界です。アメリカと財界の要求のままにTPPに突き進むならば、国民生活と日本経済は大打撃を受けることは避けられません。
第1に、TPPへの参加は、国民への安定的な食料供給を土台から破壊します。関税がゼロになれば、農林水産省の試算では、現行40%の食料自給率が13%に急落し、米の生産の90%は破壊され、農林水産物の生産は4兆5,000億円減少、雇用も350万人減るとしています。特に東日本大震災で大きな被害を受けた東北3県の農林水産業は、TPPで壊滅的な打撃を受け、震災からの復興の基盤を奪うものと考えますが、区長の見解を伺います。
第2の問題は、日本の貿易制限が規制緩和、あるいは撤廃され、アメリカ型のルールが強要される危険です。アメリカの通商代表部の外国貿易障壁報告書に、対日要求が明示され、そこには牛肉のBSE対策に対する規制緩和、残留農薬や食品添加物の規制緩和、遺伝子組み換え食品の表示義務撤廃など、日本国民の食の安全を脅かす要求が列挙されています。
医療では、混合診療の全面解禁や株式会社の病院経営への参入、HIVで大問題になった血液製剤を初め、医薬品等の輸入規制撤廃を要求しています。混合診療が全面解禁されれば、健康保険が適用されない自由診療が拡大され、金持ちしかよい医療が受けられないなど、日本の公的医療保険制度が解体されてしまうとして、日本医師会や日本歯科医師会などが強く反対しています。
さらには、政府や自治体が行っている公共事業や物品購入などの官公需に、米国企業を参入させることも要求しています。本区を初め、地方自治体が行っている地元の中小企業や建設業者などへの優先発注、あるいは分離分割発注なども、受注機会を阻害する貿易障壁だとして廃止の危険が指摘されているのです。区民の命と暮らしを脅かし、本区の地域振興策も否定するTPPに対して、区長の見解を伺います。
TPP参加は、アメリカの言われるままに日本を売り渡す亡国の道です。全国の農業団体や医療団体、消費者団体、中小業者団体などが連日反対運動を繰り広げ、TPP参加に反対する国民世論が日に日に高まっています。既にTPP参加に関する意見書が44の道府県議会で採択され、市町村を入れれば全国の約8割の地方議会が「反対」、または「慎重な対処」を求めて政府に意見書を提出しています。区長として、政府に対し、TPP参加撤回の要請を行うことを強く求め、私の質問を終わります。(拍手)
2011年第3回定例会-正保幹雄議員(保育・高齢者・障害者・中小企業・雇用)
2011年9月26日(水)2011年第3回定例会-正保幹雄議員
- 保育問題について
- 高齢者・障害者の生活支援について
- 中小企業支援と雇用・仕事確保について
[議会発言映像=クリック](区議会サイトへ)
日本共産党江東区議団を代表して、大綱3点について質問します。
第1は、保育問題について伺います。
まず、待機児童問題です。本区では、区立保育園など認可保育所に入所を希望しながら入れない児童が毎年1,000人を超え、仕方なく保育料が高く、こどもの成長にとって重要な園庭やプールが十分でない認証保育所などの認可外保育施設に入所しています。その結果、ことし4月1日の待機児童の数は273人と、この傾向は変わりません。待機児童の現状についての区の認識を伺います。
この深刻な事態は、前政権が規制緩和、民間委託、民営化を掲げ、必要な認可保育所をつくらず、認可外の保育施設を待機児童の受け皿にした安上がりの待機児童対策の破綻を示すものです。現政権も規制緩和の流れを進めていますが、規制緩和路線を転換し、国と自治体の責任による認可保育所の本格的な増設と保育環境改善の方向に踏み出す以外、待機児童問題の根本的解決はないと思いますが、見解を伺います。
前政権が2004年に、公立保育所への国庫負担金を廃止し、一般財源化したことで、自治体では保育予算を削減せざるを得ず、区立保育園の民営化、建設の抑制が行われてきました。国に対し、公立保育所の建設費、改築費への国庫補助の復活を求め、新設や改築による定員増と耐震化を促進すべきです。
また、国や都に対し、国有地、都有地の優先利用、無償貸与、土地取得に対する助成を強く求めるべきです。あわせて伺います。
次に、区立保育園の民営化問題について伺います。
区は、父母や保育関係者の願いに反して、新たに4園の民営化を打ち出しました。区立保育園の民営化は、保育士の総入れかえにより児童に多大な負担を強いるものです。委託先の社会福祉法人では、補助金の削減で人件費を切り下げざるを得ず、よりよい保育水準を確保するのは困難だという声が上がっています。
区は、委託先として株式会社を視野に入れていますが、保育は人件費の比重が極めて高い事業であり、人件費を大幅にカットして保育の質を大胆に切り下げない限り、営利を目的とした株式会社が利益を実現することはできません。安上がり、効率主義最優先の区立保育園の民営化は直ちにやめるべきです。伺います。
保育所の面積基準の緩和についてです。
国は、待機児童が多く地価が高い地域は、保育室の面積基準を都道府県が定めてよいとし、江東区もその対象に指定されました。既に東京都は待機児童解消を名目に、ゼロ歳児、1歳児の保育室面積を、現行の3.3平米から2.5平米に引き下げる条例を検討しています。厚生労働省の委託研究では、現在の最低基準以上の空間が必要だと指摘していますが、面積基準の引き下げが児童に与える影響を区はどう考えているのか。詰め込みによる待機児童解消をやめ、本区におけるゼロ歳児5.0平米、1歳児3.3平米の現行の面積基準を維持し、さらに拡充すべきです。あわせて見解を伺います。
区立保育園におけるゼロ歳児保育、延長保育の拡充について伺います。
区職員労働組合の調査でも、区として必要な保育施策の要望で一番多いのがゼロ歳児保育、延長保育です。しかし、区立保育園におけるゼロ歳児保育は、33園中18園でいまだ実施されておらず、延長保育は13園が残されています。区が責任を持つ区立保育園でこそ父母のニーズにこたえ、思い切って拡充すべきです。伺います。
障害児保育について伺います。
現在、区立保育園では、発達障害児の早期発見・早期対応のため、心理相談員の巡回指導が継続的に行われています。ところが、1,400人の児童が通っている認証保育所では実施されていません。区が、認証保育所への運営委託料に含まれているとして保育所任せにしているからです。認証保育所においても、区が責任を持って発達障害児の早期発見・早期対応を行うよう指導、援助すべきではありませんか。
病後児保育について伺います。
現在、猿江と豊洲の2カ所で実施していますが、区内全域をカバーすることは困難です。保護者の利便性などを考慮し、地域的な増設を求めます。伺います。
第2は、高齢者・障害者の生活支援についてです。
介護保険法の改正に伴う制度見直しについて伺います。ことし6月に介護保険法が改定され、これによって来年4月から軽度の高齢者へのサービス切り捨てや、介護療養病床の廃止方針の継続など、多くの問題点が指摘されています。今回の法改正による介護保険制度の見直しについて、見解を伺うものです。
とりわけ要支援と認定された高齢者への介護について、介護予防・日常生活支援総合事業を本区が導入した場合、要支援者へのサービスを従来どおり保険給付とするか、保険外の総合事業とするかを選択することができます。
保険給付のサービスと違い、総合事業にはサービスの質を担保する法令上の基準がありません。費用負担を減らすため、生活援助やデイサービスをボランティアに任せるなどの事態が起きかねません。症状が軽いというだけで保険給付の対象から外し、安上がりの事業にゆだねることは、介護を予防する上でもあべこべの対策です。要支援者切り捨ての総合事業を導入せず、介護サービスの低下を来さぬ対応を図るべきですが、伺います。
地域包括支援センターの拡充について伺います。
地域包括支援センターは、高齢者のきめ細かい相談や家族介護への支援、権利擁護事業など、地域包括ケアの中核としての役割が求められています。しかし、介護予防ケアマネジメントの過重負担など、少ないスタッフで数多くの案件を処理している状況にあり、現在の人員だけでは困難です。人員を増員配置するなど、その役割が果たせるよう一層の体制整備が必要です。また、区直営の基幹型地域包括支援センターの整備を求めます。あわせて伺います。
特別養護老人ホームの増設についてです。
本区では、2,000人近い方が特別養護老人ホームの入居を申請しているにもかかわらず、今後の整備計画はわずか1カ所だけです。このままでいいのですか。特別養護老人ホーム待機者の早期解消に向け、緊急整備促進計画を策定し、思いやりとスピードを持って積極的に取り組むべきではありませんか。
国が基盤整備の予算を削減しているこ
とは問題です。国や都に対し、特別養護老人ホーム整備などへの補助金の復活、用地取得への支援など、財政支援を求めるべきです。あわせて伺います。
次に、国民健康保険料の負担軽減についてです。
ことし4月から国民健康保険料が大幅に値上げされ、区役所に3,000件の問い合わせが殺到しました。本区では、加入者の5人に2人が滞納になっており、保険料の引き上げはさらに滞納者をふやし、病気になっても医療を受けられない区民がふえることになります。
今回の保険料引き上げは、低所得者や多人数家族、障害者世帯などが負担増となります。これらの世帯への影響を踏まえ、区独自の福祉施策として負担増の部分を補助し、保険料の軽減を図るよう求めるものです。伺います。
国に対し国庫負担の計画的増額を求めるとともに、所得に応じた保険料に改めることで滞納もなくし、持続可能な国保財政の道を開くことができると考えますが、区の見解を求めます。
後期高齢者医療保険料の軽減についてです。
高齢者の負担増を避けるため、国と都に対し財政支援を強く求め、保険料の軽減を図るべきと思いますが、伺います。
障害者への支援拡充について伺います。
本区では、視覚障害者への選挙の通知や福祉タクシー券などを送付する際、点字シールを張っています。区のどの部署から送られてきたのかがわかり、大変助かるといいます。この点字シールを医療保険課からの通知や健康診断の案内にも貼付してほしいという声が寄せられていますが、拡充を求めます。伺います。
通所施設への送迎についてです。
区は、送迎サービスを行う通所支援施設に対し、送迎費用を助成しています。この事業の財源は、来年3月末終了の国の障害者自立支援対策臨時特例交付金を活用しているため、送迎事業の継続が障害者と家族、事業所にとって死活問題となっています。事業継続できるよう、国や都に財源確保を求めるとともに、区独自の施策として、送迎事業の再構築を図るべきと思いますが、伺います。
第3に、中小企業支援と雇用・仕事確保について伺います。
本区の中小企業は仕事量が一向に回復せず、先の見通しのないまま、3月11日の東日本大震災と原発事故により、一層深刻な打撃を受けています。区は、区内中小企業の危機をどう認識し、打開を図っていくのか、伺います。
区の景況特別調査によれば、大震災によって約6割の企業が被害をこうむり、売り上げを減少させました。区内の中小企業の中には、被災地域に立地する工場、営業所、倉庫などが甚大な直接被害を受け、何とかしてほしいという切実な声が上がっています。区内中小企業の事業継続を支援するため、被災地の工場の建てかえ、修繕などに対し、都と連携して震災の影響に対応した総合的な支援策を講じるべきと思いますが、伺います。
次に、受注機会の確保について伺います。
官公需法は中小企業者の受注の機会の増大を明記しています。本区の2009年度の工事、物品の地元発注率は、件数で53%、金額で66%です。接待用のお茶や文房具、または防災備蓄物資などを区外から購入していますが、区内でも十分調達できるはずです。区内中小業者への発注率を高め、さらなる受注機会の確保を図るべきです。
適正な労働条件の確保について伺います。
官公需は公契約の一つであり、その受注額は、受注事業者の労働者に適正な労働条件を保障するものでなければなりません。
新宿区では、公共サービス基本法に基づいて要綱を定め、落札業者に「労働環境チェックシート」を提出させて、現場労働者の賃金や労働条件を把握しています。本区でも、適正な労働条件の確保など、必要な施策を講じるべきです。伺います。
また、入札の総合評価について、労働条件の確保や区内労働者の雇用実績などを評価に盛り込むべきです。伺います。
住宅リフォーム助成について伺います。
住宅の改修を地元業者に発注した場合に、経費の一部を補助する住宅リフォーム助成制度は、東京23区では足立区、大田区、品川区、目黒区、北区、渋谷区で実施、全国40都道府県330自治体に広がっています。
千葉県船橋市では、工事費の1割、上限10万円を商品券として交付します。本区でも、地域経済活性化基本条例に基づく具体施策として、住宅の改修や耐震化を実施した区民に対し、工事費の一部を江東区商店街連合会が発行する区内共通商品券として交付し、区民との協働で地域経済の活性化を図るため、区独自の住宅リフォーム助成制度を創設すべきと考えますが、伺います。
雇用の創出について伺います。
本区では、国の交付金を財源として緊急雇用創出事業を実施し、この3年間で75事業、延べ976人の雇用が創出されています。地域の雇用情勢がいまだ厳しい中、同報無線の難聴地域実態調査や介護や医療分野などの雇用創出など、重点分野雇用創出事業も活用した新たな雇用の受け皿をつくっていくべきと考えますが、見解を伺い、質問を終わります。(拍手)
2011年第3回定例会-そえや良夫議員(防災・放射能・行革)
2011年9月22日(木)2011年第2回定例会-そえや良夫議員
- 防災対策について
- 放射能汚染と自然エネルギーの活用について
- 行革問題について
[議会発言映像=クリック](区議会サイトへ)
日本共産党区議団を代表し、大綱3点について質問します。
第1は、防災対策についてです。
東日本大震災後、今後予想される地震規模と被害想定などについて、各自治体で見直しが進められています。港区では、想定される津波の高さを現行の2倍、10メートルに引き上げ、また、一斉帰宅抑制のための物資備蓄を企業や事業者に求めるなど、マニュアルの見直しに取りかかりました。
練馬区長は、早急に地域防災計画の総点検と万全な防災体制の構築を表明、足立区では、庁内緊急体制の強化、初動対応についての個別マニュアル策定など、被害想定と対策の見直しに取りかかっています。
ところが、本区では、前定例会での地震規模と被害想定の見直しを求める同僚議員の質問に、国や都で防災計画を修正したら区も見直しを図ると、大変消極的でした。大震災から区民や滞在者を守るという自治体の本旨に沿って、国や都の計画策定待ちではなく、被害想定の前提をマグニチュード9、震度7に引き上げて、現行災害対策の総点検と必要な対策の見直しに速やかに取りかかるべきです。伺います。
次は、保育園、病院の耐震補強についてです。
都営住宅1階部分にある区立保育園のうち、7園ではいまだに耐震補強の計画がありません。速やかな実施を求めます。特に辰巳第二、第三保育園が、都営住宅建てかえを理由に、10年後、12年後まで先送りとなっているのは問題です。耐震補強工事をまず最優先で行うべきです。伺います。
被災地では多くの病院も壊滅的被害を受け、救急救護体制に重大な支障を来しました。病院の耐震化は、被災した区民の命を守る上で最優先の課題です。区内医療施設の状況を区としても把握し、補助引き上げなど、耐震化の促進への支援を強化すべきです。あわせて伺います。
次は、個人住宅の耐震改修についてです。
個人住宅の耐震補強のおくれは依然深刻です。建物倒壊から命を守るための対策強化が必要です。区はこの間、部分改修、耐震シェルター設置に対する助成について、建物の安全面に課題が残る木造住宅の部分補強は対象外との答弁を繰り返してきました。区民の命をまず守るという姿勢が見られません。23区中15区では、高齢者世帯などを対象に、部分改修、耐震シェルター設置に対する助成を始めました。本区でも速やかに助成を始めるべきです。伺います。
次は、発災時の通信手段についてです。
3月11日の発災後、都内でも携帯電話がつながらないという事態が長時間にわたって続いたため、公衆電話の前に大行列ができました。公衆電話があまりにも少な過ぎます。一時避難場所となる木場公園の周りにも1台しかありません。外出中に地震に遭ったら、安否確認さえままならない状態です。
コンビニエンスストアでは、災害時には公衆電話を各店舗に設置するとのことですが、災害時の通信手段確保は本来、国とNTTの責任です。コンビニエンスストア任せではなく、国とNTTに対し、屋外公衆電話の大幅増設を求めるべきです。伺います。
次に、障害者の災害時安全対策と避難所確保についてです。
本区内には82カ所の民間通所作業所やグループホームがあり、1,200人の障害者が利用しています。しかし、これらの施設の中には老朽化したものも多く、早急な耐震補強を求める声が寄せられています。速やかに実態を調査し、一日も早く耐震補強ができるよう支援を強化すべきです。伺います。
障害者のための避難所の整備のおくれ、受け入れ態勢のあり方も問題です。前定例会では、福祉作業所を含めた2次避難所の拡充を検討との答弁がありました。しかし、障害認定を受けている人7,000人に対し、2次避難所は17カ所、受け入れ人数はわずか450人程度です。しかも備蓄物資の準備もありません。深刻なおくれです。認識を伺います。
2次避難所という位置づけ自体が問題です。先に1次避難所に行って判定を受けなければならないという今の仕組みは、障害者には大変な負担です。位置づけを福祉避難所と改め、事前に各人が入れる避難所や連れていってくれる人を決めておき、真っすぐに行けるようにするべきです。そのためにも福祉避難所の増設と受け入れ人数の大幅な引き上げを図るべきです。あわせて伺います。
最後に、災害時の学校用務員の位置づけです。
前定例会での同僚議員の質問に、区は、用務員は各校ごとにつくる防災態勢の中で位置づけられると答えましたが、実態は学校任せで、位置づけは各校ばらばらです。このままでは大災害時に区民を守るための十分な力が発揮できません。実態を調査し、校内や地域の事情に詳しい用務員を、防災態勢に位置づけるよう指導すべきです。伺います。
第2は、放射能汚染と自然エネルギーの活用についてです。
福島原発事故によって大量の放射能が広範囲に放出され、国民の間に不安が広がっています。放射能への感受性が強いこどもの健康を守ることは、日本社会の大問題です。放射能汚染の実態を正確につかみ、被曝は少なければ少ないほどよいとの最新の科学的知見を踏まえ、区民の命と健康を守るためにあらゆる手だてを尽くすことが必要です。
本区が校庭、園庭や公園516カ所で行った空間放射線量の調査は大事な一歩です。しかし、側溝や雨水ますとその周辺など、詳しい調査を求める声が寄せられています。放射能からこどもたちをできるだけ遠ざけるためにも、よりきめ細かく調査すべきです。こどもたちの遠足などにも利用される夢の島公園や木場公園、猿江恩賜公園、亀戸中央公園などの都立公園は、いまだ調査もされておりません。速やかな調査を都に求めるべきです。あわせて伺います。
原発事故は、収束の見通しも立たず、放射能の放出も続いています。事故収束まで調査を継続し、その結果を教職員、保護者にわかるように公表するとともに、年間1ミリシーベルトを超える場所については、速やかに除染すべきです。伺います。
次に、食品の検査体制についてです。
食品の検査は厚生労働省が都道府県に行わせていますが、検査機器も体制も不十分なために、実態の正確な把握にはほど遠く、こどもの保護者などに大きな不安を広げています。政府が決めた食品の暫定規制値を超える食品を、市場に絶対流通させないことはもとより、暫定規制値の検証、見直しが必要です。
また、放射能汚染に責任のない生産者に損害を与えないための万全の態勢も必要です。そのためにも、国の責任で最新鋭の検査機器を最大限に確保して、検査体制の抜本的強化を図るとともに、暫定規制値の見直しを進めるよう求めるべきです。伺います。
本区も給食食材の産地表示を開始しました。しかし、産地の検査体制の現状を踏まえたさらなる対応が求められています。
杉並区では、区民の納得を得るためにより細かい値を出したいとして、放射性セシウムの測定器の導入を決めました。本区でも食材の独自測定と数値の公表を行うべきです。伺います。
次に、原発事故と原子力発電に対する認識についてです。
福島原発の事故で放出されたセシウム137は、広島型原爆の168倍、海洋への放射能放出量は1.5京ベクレルと天文学的です。しかも、これを抑える技術はなく、汚染地域は限りなく広がり、原発周辺の地域丸ごと存続を危うくする事態となっています。
また、原子炉の老朽化が進み、緊急停止したときに壊れる危険性が指摘されているものもあります。使用済み核燃料の貯蔵量は限界に近づき、その処理技術も確立されていません。原発事故の異質の危険性と原発に関する技術の未完成な現状について、区長の認識を伺います。
次に、原発からの撤退についてです。
原発推進の理由に、発電コストが一番安いとの主張があります。しかし、設備利用率や耐用年数、国家財政からの資金投入など、実態に即してコストを計算すれば、原発が一番高いとの試算もあります。いつまでも原発にしがみつく理由はありません。
福島県浪江町は原発交付金の受け取りを拒否し、福島県も原発からの撤退を表明しました。前定例会で区は、エネルギー政策は国の問題と答弁しましたが、区民の命と健康、地域社会を守ろうとするのかどうか、区長の姿勢が問われています。次世代に危険と負担を残さないよう、速やかに原発から撤退し、自然エネルギーへ切りかえるよう、国に求めるべきです。見解を伺います。
最後は、自然エネルギーの活用についてです。
我が党区議団は、先月、日本初の地熱発電所である松川地熱発電所と、エネルギーの地産地消体制構築を目指す岩手県葛巻町を視察してきました。
同町では、既に町で必要とする電力の160%を風力や太陽光、バイオマスなどで発電しています。また、その過程において町で働く人に雇用と所得が生まれているとも言います。今、温暖化防止と同時に、原発からの撤退を進めることが求められています。区が率先して、公共施設の屋上や壁面などへの太陽光発電パネルの設置や省スペースの縦型風力発電機の設置などに取り組むべきです。
また、区内の大型マンションやオフィスビルの建設、改修に当たって、屋上や壁面への太陽光パネル設置など、自然エネルギーの活用を求めるべきです。あわせて伺います。
環境省は、個人住宅への設置拡大とその促進のための補助の拡大が、再生エネルギー拡大のかなめとしています。国に対し補助拡大を求めるとともに、本区の独自補助も引き上げるべきです。伺います。
最後は、行革問題についてです。
区が新たに発表した行財政改革案は、新たな時代に即したものとしていますが、その特徴は、社会保障に対する国の責任放棄と地方切り捨てを柱とする地方行革を一層推し進める地域主権改革の引き写しにほかなりません。
本区では、この10年来、毎年1万人の割合で人口がふえ続け、行政需要も猛烈な勢いで増加してきました。そうした中にあって区は財政危機をあおり、保育料や自転車駐車場利用料を初め、各種利用料や使用料を値上げしてきました。また、効率化の名目で正規職員を削減し、民間委託の拡大で低賃金労働者への置きかえを進めてきました。
保育園や特別養護老人ホームの増設は民間任せで、特別養護老人ホームの入所待ちは1,950人を超えています。こうしてため込んだ区の基金総額は、決算ベースで800億円を超えています。
新たな行革案は、不況にあえぐ区民に保育料を初め、使用料や利用料の値上げなど、さらなる負担増を押しつける一方、特別養護老人ホームの増設計画は既に決まった1カ所だけなど、自治体の使命を置き去りにした理念なきため込み主義と言わざるを得ません。ため込む前に区民の負担を和らげ、区の責任で足りない特別養護老人ホームや認可保育所を増設するなど、区民福祉向上に力を尽くすべきです。伺います。
次は、職員定数についてです。
新たな定員適正化計画では、技能系職員を単純労務職員と決めつけて、その採用は原則として行わないとしています。これは人を職業、業種で差別する考え方であり、断じて許せません。また、差別をなくし、対等で平等な社会実現に力を尽くすべき自治体の役割に照らしても、あってはならないものと考えます。区長の見解を伺います。
新たな削減対象とされた現業系職員、例えば土木事務所の職員は、道路の傷みや道路標示の不備などを常時見守り、改善するとともに、区民からの通報にも速やかに対応するなど、区民の安全確保に日ごろから大事な役割を発揮しています。また、集中豪雨などの折には、区民生活を守るために最前線で体を張って頑張っています。長年の経験に基づく判断力と公務員としての高い自覚を持って働き、その仕事ぶりへの区民の評価も高い、この大事な職員を際限なく減らす根拠は何か。区長が考える適正な定員数とはどのような基準で決めるのか。基本的な考えを伺います。
際限のない職員削減は、防災対策上も問題です。大地震の際には、区の職員が休日返上で対応し、区民に喜ばれました。被災地からは、みずからも被災しながら住民を守り必死に働く自治体職員の姿が報道されています。しかし、今現地では、復旧・復興に当たる職員の不足が大きな問題となっています。
復興担当大臣は、NHKのインタビューで、地方行革による職員削減が原因だと答えています。本区では、10年前と比べ、人口が8万人近くふえたのに職員は800人も減らされ、人口1,000人当たりの職員数は9人から6人となりました。いざというときに区民を守る体制が大幅に弱められました。認識を伺います。
民間委託の拡大は、社会的、経済的にも問題です。
学校の給食調理では、266人の正規職員が、時給1,000円程度の年収百数十万円の低賃金労働者に置きかえられ、所得低下の一因となりました。
また、ある自転車保管場所では、入札による契約価格引き下げを口実に、法律で決められた最低賃金さえ支払われていませんでした。また、別の自転車駐車場では、少し離れた場所にあるもう1カ所の機械式自転車駐車場の故障に備え、職員が常時2人以上詰めるとの契約条件を受託業者が守らなかったために、利用者とトラブルになり、退職に追い込まれる事態も発生しました。こうした事態は議会で取り上げられるまで放置されていました。
民間委託の拡大は、事業者の雇用に対するモラルハザードと所得の低下を招き、景気悪化と区税収入減少の原因を、区みずからがつくり出すものとなっています。区長の認識を伺います。
非正規雇用の拡大や不況などを理由にした賃金引き下げが景気悪化の原因との認識は、財界系シンクタンクの専門家からも広く指摘されています。景気の悪化、区税収入の減少を食いとめるためにも、まずは区が民間委託の拡大計画などを取りやめ、正規職員の採用をふやすべきです。
以上を伺い、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
再質問
再質問2点です。
まず、1つは、障害者の2次避難所についてですけれども、整備がおくれているかどうかの認識について、答弁がなかったかと思います。これは今後の取り組みにかかわる問題なのできちんと答弁願いたい。
それから、原発の異質の危険性に対する問題について、これについてきちんと考え方を示すべきだというふうに思いますので、再度答弁を求めます。